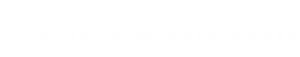Forguncy開発スキルの平準化・底上げのため教育サービスを活用!
富士航空電子株式会社 様
>>富士航空電子株式会社 様 ホームページはこちら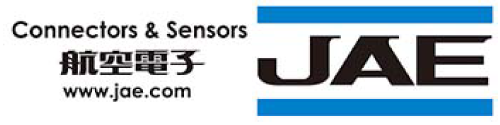
富士航空電子株式会社 様
総務部 情報システムグループ
鳥塚 葉子 様
主な事業内容:
日本航空電子工業グループの一員として、精密な金型の設計・製作を中心に事業を展開しています。
受講内容
基礎学習コース、実践コース、オプションAコース(テーブル設計とDB周りの設定)、オプションBコース(ワークフロー・再利用コマンド・リストビュー)
現在のForguncyの活用状況についてお聞かせください
Forguncy導入から1年半が経ち、導入時はシステム開発経験者1名、未経験者3名で開発をスタートしましたが、現在では全体で7名にまで担当者が増えました。
新しく参加してくれた担当者もシステム開発未経験者ではありますが、導入してから今までの1年半あまりで、社内アプリを10件以上リリースし、社内での利用も進んできています。
Forguncy教育サービスを受けようと思った理由はなんですか?
これまではシステム開発経験者が未経験者に教えつつ、各担当者が独学でアプリを開発・リリースしてきました。ですが、システム開発経験者と言えどForguncyには初めて触れるため、教えられる内容には限界があること、今のままではForguncyの機能の一部しか使えないままになってしまうと感じたことをきっかけに教育サービスを受講しました。
また、独学で進めてきたがゆえに作成してきたアプリによって開発者の使う機能に偏りが見られ、スキルの平準化・底上げの必要性を感じたことも理由のひとつです。
今回受講された方は、どのような方になりますか?また、どのように人選されましたか?
今回は、システム開発未経験者の6名に、基礎コースを3名、実践コースを3名に分かれて受講してもらいました。コースの振り分けは、Foruguncyでの開発年数を基準にし、導入当初から携わってきた3名に実践コース、新しく参加してくれた3名に基礎コース、というように分けました。
オプションコースにつきましては、システム開発経験があるものが受講しました。
Forguncyを使った開発において、難しいと感じている点はありますか?
担当者からよく聞くのは、変数を使ったコマンドや、クエリでのデータ絞り込みなど、「こう設定したらこうなるはず」と想像する部分がつかみにくいようです。
また、コマンドも、基本的な使い方はできるものの、各コマンドのオプションに隠れている機能までは見きれておらず、「そんな機能もあったのか…」とあとから気づくことも多いです。
Forguncyの教育サービスを受講されてみていかがでしたか?
基礎コースは、テキストに沿って実際の画面を作りながら教えていただくことで、Forguncyの基本的な操作から少し踏み込んだ内容まで、いろいろと知ることができたと受講者から話がありました。思っていたよりも内容が盛りだくさんで、新しいことも知ることができたようです。
実践コースは、課題を進めながら疑問をぶつけていくスタイルでしたが、テキストがとても丁寧に作りこまれていたことでかえってあまり疑問が出ず、受講者としても少し困っていたようです。「課題のアプリを機能強化するとしたらどういう機能を付けたい?」と投げかけてみたところ、いろいろとやりたいことが出てきたようなので、実践コースがどういった方法で進んでいくのか、事前にもう少し詰めておくべきだったと思っています。ただ、週1回の講義だけでなくTeamsなどで質問をした際には、講師の方に随時対応いただき、受講者も受け身ではなく自発的に受講できたのはとても良かったと感じています。
教育サービスについて、問題点や改善してほしい点はありますか?
実践コースで出される課題については、もう少し大まかな情報(機能や条件)だけを与えて自分で考えさせる方がより効果的になるのではと思います。
テキストやヒントがほぼ解答になってしまっているので、使ったことのない機能でも悩むことなく課題を作ることができてしまい、「うまくいかない」という壁にぶつかることがほとんど無かったようです。
教育サービス受講後のForguncy開発について今後の展望があればお教えください。
教育サービスを受講したことで、各担当者のスキルレベルを把握することもでき、また一定の底上げもできたように思っています。
ただ、これを維持するためにはやはり日々何かしらの開発に携わっていることが1番重要ではないかと思うので、社内からの要望があればもちろんですが、今回得た知識をもとに私たちから改善策を提案しながら、社内のDX化を進めていけたらと考えています。